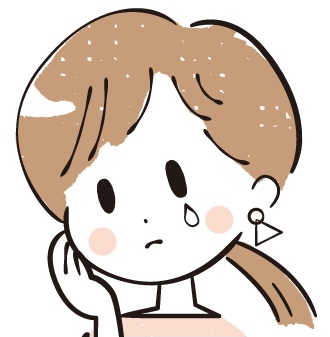
朝起きると、頭が痛くて肩も重い…。
1日の始まりである朝。
朝の目覚めが悪いと、その日は気分も落ち込みますよね。
寝起きに頭痛や肩こりを感じるなら、なおさら!
寝起きに感じる頭痛や肩こりには、主に3つの原因が考えられます。
そのまま放置すると、悪化してしまう可能性が…!!

そうなの!?
朝の頭痛や肩こりは、原因を知って正しい対処をすることで改善できます。
寝起きに頭痛や肩こりを感じる場合は、基本的に睡眠の改善が大前提!
偏頭痛に関しては、睡眠の改善だけでなく、専門機関での治療が必要となります。
今回は、寝起きの頭痛や肩こりの原因3つとその改善方法まで解説していきます。
まずは、あなたの頭痛や肩こりの原因から考えていきましょう!
寝起きの頭痛や肩こりは朝型肩こり!?自律神経の乱れ!

朝に目覚めると、体の疲れがスッキリせず、頭痛や肩こりも…。
これはズバリ「朝型肩こり」!
- 朝型肩こり
- 朝型肩こりは、自律神経の乱れから生じる不眠が大きな原因で起こります。
【自律神経が乱れる主な6つの原因】
1.ストレス
2.冷え
3.姿勢
4.歯ぎしり
5.肩の疲労
6.眼精疲労 - 【改善方法】
生活習慣の見直し
- 消化や呼吸などの活動を調節している神経
- 交感神経と副交感神経からなる
- 交感神経は昼間に活性化し、副交感神経は夜間に活性化する
自律神経は、私たちの身体の活動を無意識下で適切に調節してくれますが、過度のストレスなどでバランスを崩すことも。
すると、夜間でも交感神経がよく働くようになり、眠りにくくなってしまいます。

忙しいから仕方ないのかな。
あなどってはいけません!
朝型肩こりを放置すると、頭痛や目まい、便秘のような消化器症状にまで発展してしまいます。
あなたの体の不調も朝型肩こりが原因かも。
まずは、生活習慣を見直して、「頑張りすぎないこと」を意識してみましょう。
あなたが頑張っているのと同じように、あなたの身体も頑張っています!
あなた自身とその心と体も労わってあげてください。
注意してほしいのは、寝起きに感じる肩こりと夕方に感じる肩こりは異なるものだということ。
朝型肩こりは精神的な疲れも原因に関わるのに対し、夕方の肩こりは単純な疲労が原因であることが多いです。
夕方に肩こりを感じる場合は、軽いストレッチや肩などの温めを行うアプローチが効果的ですよ。
【原因】6つの大きな原因とその対策
朝型肩こりは、自律神経の乱れによる不眠が大きな原因。
睡眠の質を下げ、寝起きの頭痛を引き起こす原因は人それぞれですが、大きな原因を6つご紹介します。
| ストレス | 休む間もなく勉強や仕事をする |
| 冷え | 夜のコーヒーやお茶 |
| 姿勢 | 長時間のデスクワーク |
| 歯ぎしり | 日中および睡眠中の歯ぎしり |
| 肩の疲労 | 合わない枕の使用 |
| 眼精疲労 | 寝る直前のスマホやパソコンチェック |
1.ストレス
年度末などの忙しい時期には、特にストレスが溜まりますよね。
そのような時期には、ストレスによる自律神経の乱れが起こり、朝型肩こりを訴える人が増えるそうです。
ストレスは自律神経を刺激して、交感神経がよく働くようになってしまいます。
すると、就寝中も筋肉が固く縮こまった状態に…!
ストレスは、首や肩の筋肉を常に緊張させ、不眠や寝起きの首こり・肩こりにつながってしまうのです。
【ストレスへの対策】
対策としては、日中に軽く体を動かしてストレス発散するのが一番!!
私は運動が苦手ですが、家でyoutubeを見ながらストレッチをしたり、晴れた日は少し散歩をしたりします。
ほんの少しでも動くと気分もリフレッシュできますよ!
また、就寝前のストレッチで筋肉をほぐし、自律神経を副交感神経優位な状態(リラックス状態)にすることも効果的です。
2.冷え
冷えは、血行を悪くして寝起きの頭痛や肩こりの原因に。
冬の寒い日はもちろん、夏場でもエアコンを付けたままで寝てしまうと、体は想像以上に冷えて筋肉がこわばってしまいます。
【冷え対策】
就寝前にゆっくりとストレッチすることで、血行改善するのが効果的。
コーヒーやお茶は温かい状態でも体を冷やしてしまうので、就寝前はNGです。
寝る前に飲みたい場合は、ノンカフェインのお茶がオススメ。私の場合は、就寝前のルイボスティーが定番です。
3.姿勢
姿勢の悪さは、寝起きの頭痛や肩こりにつながります。
猫背やストレートネックなどの悪い姿勢が習慣化すると、身体の骨格が歪み、睡眠時の姿勢も悪くなります。
また、身体に合わない枕を使い続けることによって首や肩に負担が…!
合わない枕は、寝起きの頭痛や肩こりの原因になってしまうのです。
枕については別の見出しで詳しく紹介しているので、そちらも是非ご覧ください。⇒【改善方法】枕の高さと幅を見直そう
【悪い寝方への対策】
日中は正しい姿勢を心がけ、悪い姿勢によってこわばった筋肉をほぐしてあげましょう。
4.歯ぎしり
意外なことに、歯ぎしりも寝起きの頭痛や肩こりの原因に。
歯で何かを噛みしめる時に使われる筋肉は、ほとんどが顎から首、肩へとつながっています。
歯ぎしりをすると、顎・首・肩の筋肉が緊張状態となり、寝起きの首こりや肩こり、頭痛などを引き起こしてしまうのです。
【歯ぎしり対策】
夜寝るときにマウスピースを付けることが有効。
マウスピースによって、歯ぎしりによる筋肉の緊張を緩和することができます。
日中にも歯を食いしばる癖がある場合は、噛みしめないように意識するだけで、就寝中の歯ぎしりを軽減させることができます。
5.肩の疲労
通常、日中にたまった疲れは睡眠中に回復します。
夜遅くまで仕事や家事をすると、睡眠不足となり、首や肩にかかる疲労が回復しきれなくなってしまいます。
【肩の疲労対策】
生活習慣を見直し、睡眠不足を改善することが一番。
また、充分な睡眠時間を確保しているつもりでも、身体がしっかりと休息できていない場合が…!
しっかり熟睡するためには、食事や飲酒、入浴は寝る2-3時間前に済ませておくのがポイントです。
6.眼精疲労
デスクワークなどを長時間続けていると、目の筋肉に過度の負担がかかり、眼精疲労の状態となります。
目の筋肉がこわばると、首や肩の筋肉にまで負担を与え、頭痛や肩こりの原因に。
デスクワーク中はこまめに休憩をはさみ、筋肉の緊張をやわらげましょう。
パソコンやスマホの画面から出る「ブルーライト」も、自律神経の乱れと睡眠不足の原因です。
【眼精疲労対策】
ブルーライトをカットできる眼鏡を活用してみるといいかもしれません。
目の周りの筋肉をほぐすことも、眼精疲労対策としておすすめ。
眼精疲労の対策として、快眠のために就寝前のスマホを控えることも大切です!
就寝前、スマホやパソコンを見ていませんか?
私もつい気になって、メールやLineをチェックしてしまいます。
ダメだと分かっていながら…。
実際、夜に急用の連絡はなかなか無いはず!
チェックするのは朝、と決めてしまうのがよいですね。
【改善方法】生活習慣を見直そう
朝型肩こりの原因は、前日や睡眠中の行動までさかのぼって考えていくことが重要です。
原因が1つだけではなく、複数が組み合わさった場合も。まずは1つでもいいので、なにか対策を始めてみましょう。
以下、朝型肩こりに対する対策のポイントをまとめました。
- 適度に休憩を取りながら作業する
- 日中の運動でストレス発散
- 寝る前のストレッチでリラックス&血行促進
- 食事やお酒、入浴は寝る2-3時間前に済ませる
- 寝るときは暖かくして眠る
眠る前は、心も体もクールダウンする時間を持つようにしましょう。また、腹式呼吸をゆっくり行いながらのストレッチも効果的です。
寝る前にほんの少し伸びをするだけでも、緊張がほぐれて眠りやすくなります。
一度にいろんなことを変えていこうとせず、少しずつあなたの生活を改善していきましょう。
寝起きの頭痛原因は片頭痛!?血管拡張の危険サイン!

片頭痛は、頭の片側に限らず、両側が痛むこともあります。
寝起きに限らず、日中に感じることも。
- 片頭痛
- 片頭痛(偏頭痛)とは、こめかみから目の辺りにズキンズキンと脈打つような痛みが起こる頭痛。
特徴は、体を動かして頭の位置を変えることで痛みが増幅することです。
【原因】
脳血管の急激な拡張
【6つの要因】
1.睡眠問題(過眠・寝不足)
2.女性ホルモン
3.空腹
4.疲労
5.強い刺激(音・光)
6.特定の食べ物(チョコレートなど)
【3つの対処法】
1.頭痛部位を冷やす
2.静かな暗所で休む
3.カフェインを適量摂取
片頭痛は、頭痛外来などの専門機関できちんと治療する必要があります。
頻度や持続時間に個人差はありますが、ひどい場合は1週間に1回、周期的に繰り返します。
場合によっては、頭痛だけでなく吐き気や嘔吐、下痢などの症状も。
片頭痛の前兆としては、眼前にちらちらと光が見えたり、音・光・臭いに対して敏感になったりする症状が先行します。
片頭痛の症状に心当たりのあるあなたは、早めに治療を受けましょう!!
【原因】血管を拡張させるさまざまな要因
何らかの要因で脳の血管が急激に拡張して起きるのが「片頭痛」です。
片頭痛の原因は、ストレスや環境変化、食べ物などさまざま。
脳の血管が拡張すると、周囲の三叉(さんさ)神経を刺激してしまいます。
- 顔の感覚を脳に伝える神経
- 脳から頭蓋骨の奥を通って顔に広がる
神経が刺激されることで、痛みを引き起こします。神経の刺激により発生した炎症物質は、さらに血管を拡張して片頭痛を発症します。
特に気を付けたいのは、心身のストレスから解放された時。
急に血管が拡張することがあります。
週末など、学校や仕事がお休みの日は開放感があり、一気に気が抜けますよね。
緊張から解放された時に頭痛を感じたら、片頭痛を疑ってしっかり休みましょう。
原因となる要素として、具体的に以下のようなものがあります。
- 過眠
- 寝不足
- 女性ホルモンの変動
- 空腹
- 疲労
- 光や音などの強い刺激
- 食べ物(チョコレート、チーズ、ハム、ヨーグルト、赤ワイン)
片頭痛の原因は、意外と身近にたくさんありますね。
私も思い当たる要素がいくつかあります。
とくに週末の二度寝は至福の時。
しかし、寝だめや二度寝はとても危険!
週末の寝だめや二度寝は、空腹と寝過ぎが重なることで片頭痛を重くするので要注意!!
寝起きには頭痛が起きてしまうかもしれません。
あなたにも経験があったでしょうか?
片頭痛は原因をきちんと知ることで正しい対処ができます。
頭痛が起きた日やその時の環境、時期をチェックしておきましょう!
診察の際にも役立ちますよ。
【対処法】痛みを和らげる3つの方法をご紹介
片頭痛は病気であり、専門機関での治療が必要です。
しかし、痛みを感じたときに少しでもその痛みを和らげたいですよね。
痛みを感じたとき、片頭痛に対して自分でできる痛みの軽減法があります!
- 冷やす
- 静かな暗い場所で休む
- カフェインを適量摂取する
痛みに困ったときは、この3つの対処法を行ってみてください。
冷たいタオルなどを痛む部位に当てることで、血管が収縮して痛みの軽減に役立ちます。
頭痛の最中に体を動かすと痛みが増し、光や騒音で痛みはさらに増してしまいます。
できるだけ静かな暗いところで横になって休みましょう。
コーヒー、紅茶、日本茶などに含まれるカフェインは血管を収縮する作用があります。
痛みの早期に飲むと痛みが軽減。
寝起きに頭痛を感じたときも、温かいコーヒーやお茶を飲むと頭痛も和らぎ、気分も落ち着きます。
少しでも楽になるように、自分でできる対処法を行ってみましょう。
【注意】診察を受ける前の片頭痛チェック
診察を受ける際に気を付けてほしいのは、片頭痛だと思っていたら、そうではなかったという場合。
実際に、自分では片頭痛だと思っている「自称片頭痛持ち」の方が大変多いそうです。
自称片頭痛持ちの方は、病院で受診しても片頭痛のような「血管性頭痛」ではないため、異常なしと診断されてしまうかも。

何でもないです。
心配いりません。
その結果、諦めて市販の薬でごまかしながら、痛みに耐えるケースも…!
どうやって片頭痛かどうか確かめたらいいの?

実は、片頭痛かどうかを確かめる簡単な方法があります!
お風呂に入ると痛みがひどくなるかどうかをチェック
お風呂に入ると血管が広がるため、片頭痛であれば痛みはもっとひどくなるはず。
お風呂では血流が良くなるので、ズキンズキンと脈打つような痛みが増幅してしまいます。
逆にお風呂に入ると頭痛が楽になる場合は、次に説明する「筋緊張型頭痛」の可能性も!
寝起きの頭痛を枕が解決!特に筋緊張型頭痛の方へ

筋緊張型頭痛は、美容師やエステティシャン、パソコンに長時間向かう方など、うつむいて同一姿勢をとり続けがちな方に多く見られます。
- 筋緊張型頭痛
- 筋緊張型頭痛とは、ひどい肩こりや首こりから生じる首後ろの筋緊張による頭痛。
頭痛を訴える方の多くが、この筋緊張型頭痛に当てはまります。
【原因】
・肩こり
・首後ろの筋緊張
【改善方法】
自分に合う枕の見直し
どんな人がなりやすいの?

筋緊張型頭痛になりやすい人には、以下のような特徴があります。
- うつむいて同一姿勢をとり続ける(立ち姿勢でも座り姿勢でも)
- 頸椎(けいつい)に疾患がある
- 首や腰にヘルニアがある
同一姿勢が続いたときは20分に1回、3分ほどでも頭を持ち上げて首を起こすことを意識しましょう。
こまめに姿勢を戻してあげることが、神経を圧迫する首の筋肉をゆるめるのに有効です。
筋緊張性頭痛は、頸椎の変形やヘルニアによって起こる場合もあり、頚椎に疾患を抱えている方や首・腰にヘルニアがある方は要注意!!
【原因】筋緊張による神経の炎症
筋緊張型頭痛は、肩こりや首後ろの筋緊張が続くことが原因で起こります。
最初は後頭部から痛みが始まり、徐々に頭全体へと広がって、やがて眉頭から眼の奥、次第に頭皮や顔面までしびれることがあります。
これは、大後頭(だいこうとう)神経が首後ろの緊張した筋肉に挟まれて、炎症を起こすため。
- 頭の付け根から出て頭の表面を前頭部に向かう神経
- 髪の毛の生えぎわあたりに存在
- 顔面に向かう三叉(さんさ)神経とリンクする
首からの神経が顔面までつながっているため、肩こりや首後ろの筋緊張が、顔面のしびれや眼の奥の痛みにつながるのです。
筋緊張性頭痛の一番多い原因は、合わない枕の使用によるものとも言われています。
もし、寝起きで頭痛や肩こりが辛い場合は枕を疑ってみましょう。
頭は約4-6㎏の重量があり、日中それを支えている首には負荷がかかり続けています。
寝起きで頭痛があるということは、日中に頭の重みを支えるよりも、合わない枕で寝る負担の方が大きいということ。
症状を改善するために、まずは「枕」という睡眠の必須アイテムを見直しましょう!
【改善方法】枕の高さと幅を見直そう
寝起きの頭痛を改善するには、枕が重要。
さまざまな研究から、睡眠時における最適な首の角度は15度と言われています!
この時、のどの呼吸も楽になり、首、肩、背中の筋肉の緊張もとれます。
筋肉の緊張がとれることで、頭痛の改善に。
15度と言われてもなかなか自分では計測できないので、専門店に行って相談してみるとよいですね。
また、寝起きの肩こりによる頭痛にも枕が重要です。
肩こりは、肩関節周辺で起こるこりや痛みのことだと思いがちですが、8-9割は首に原因と痛みがあります。
つまり、肩こりだと思っている痛みのほとんどが首こりだということ。
首には頸椎(けいつい)という骨があり、そこを脊髄(せきずい)と呼ばれる太い神経の束が通っています。
脊髄神経は頭から首、肩などの全身とつながっているため、首こりは肩こりにつながるのです。
肩こりを改善するためにも、首を休めましょう!
首こりの改善で、肩こり、さらにはそこから引き起こされる頭痛の改善へ!
本来は、睡眠時が唯一、頭の重みから解放されて首を休めることができます。睡眠時に首をきちんと休めるためには、やっぱり枕が重要。
睡眠による体の問題を感じている場合は、枕が自分の体格に合っているかどうかを基準に選んでみてください。
適切な高さの枕は、頭の位置を適切にしてくれます。すると、睡眠時にリラックスして首や首回りの筋肉を休めることが可能に。
枕が体に対して高すぎたり低すぎたりする場合は、以下のような問題があります。
- 首の筋肉の緊張をやわらげることができない
- 椎間孔(頸椎周辺の神経の通り道)を狭めてしまう
睡眠中に筋肉を休ませることができず、さらには神経を圧迫して痛みを引き起こしてしまいます。
適切な高さの枕は、ヘルニアの方や日中の姿勢に問題がある方にとっても、より良い睡眠姿勢と症状の改善が期待できます。
加えて、枕に幅があることで、きちんと寝返りをうつことができ、睡眠時の姿勢がよくなります。
高さと幅の合った枕を選んで、寝起きの頭痛や肩こりを改善していきましょう!
枕を良いものにしたら、次はベッドの配置も気になってきた…という場合はこちらもぜひ参考に♪

まとめ
- 寝起きの辛い頭痛や肩こりの原因は、主に「朝型肩こり」「片頭痛」「筋緊張性頭痛」の3つ
- 「朝型肩こり」や「筋緊張型頭痛」の改善には、「睡眠」と「生活習慣」の見直しをする
- 「片頭痛」の場合は、専門機関での治療が必要
- 肩こりの大きな原因は、「首こり」であり、首こりが頭痛の原因となる
- 睡眠の改善には、枕の幅や高さが自分に合っているかどうかが重要である
いかがでしたか。
あなたの症状に合った原因は見つかったでしょうか?
頭痛の原因に合った改善方法を行うことが大切です。
少しずつでも生活を改善して、1日の始まりを快適にしていきましょう!
気持ちのいい朝が迎えられると、その日を快適に過ごせそうですね♪

